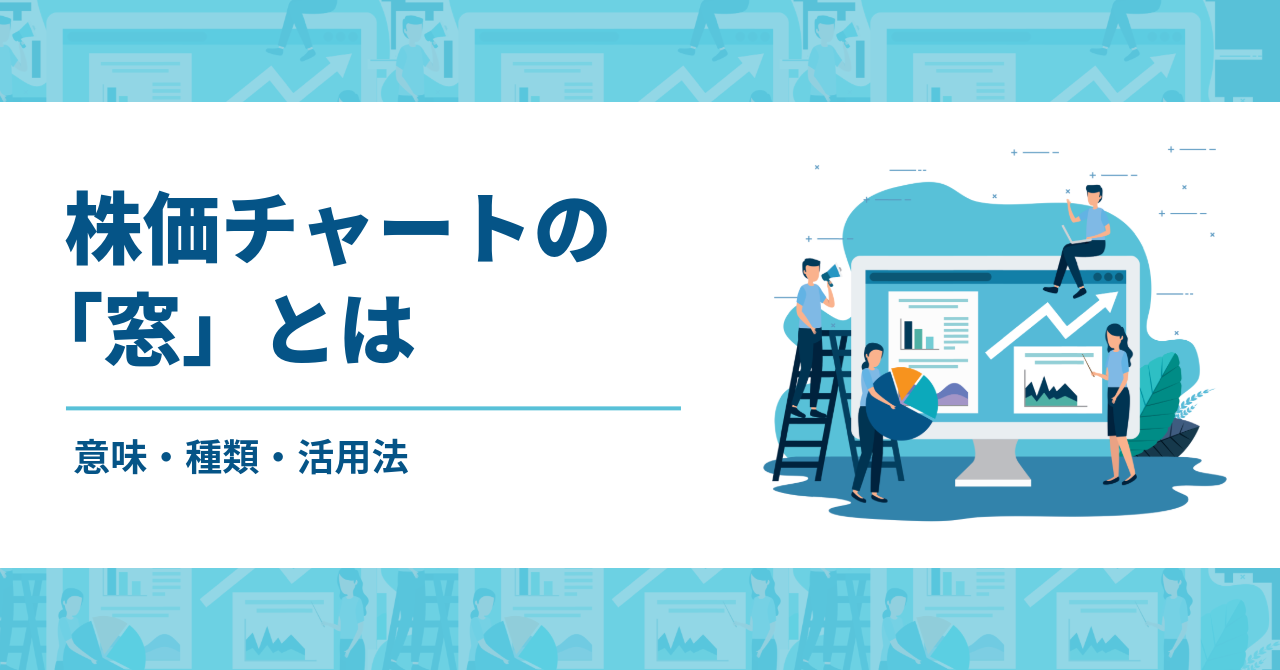株式投資の世界では、「窓(ギャップ)」という言葉がよく使われます。
「〇〇銘柄が上窓を開けてスタートした」「今日は下窓を埋めにいく動きだった」など、チャート分析をしていると当たり前のように飛び交うこの「窓」という用語。
けれども、初心者の方にとっては、「えっ?株に“窓”?どういうこと?」と感じるかもしれません。
そこで本記事では、この「窓」とは何なのか、なぜできるのか、どんな意味があるのか、そして実際の投資判断にどう活かせるのかを、図解や実例を交えて徹底解説していきます。
「窓(ギャップ)」とは何か?

チャート上にできる“すき間”=ギャップ
株価チャートでは、1日の値動きをローソク足で表すのが一般的です。
そのローソク足を見ていくと、時折「前日の終値と、当日の始値が大きく離れている」場面があります。
たとえば、前日終値が1,000円だった銘柄が、翌日の寄付きで1,050円で始まったとしましょう。
この場合、前日の高値1,010円と当日の始値1,050円の間に空白が生まれます。
この「空白」が“窓(ギャップ)”です。
整理すると、チャート上で「価格帯が抜けている部分」=窓(ギャップ)と呼びます。
なぜ窓ができるの?
窓が発生する最大の理由は、寄付き(市場が始まる時間)までに、投資家の注文が集中するためです。
たとえば…
- 夜間の決算発表で好決算が出た
- 海外市場で同業他社の株価が急上昇した
- 大きな経済指標や政治ニュースが出た
このような要因があると、翌朝の寄付きで「買いたい人」「売りたい人」が一気に増加します。
その結果、前日の終値よりも大幅に高く(または低く)始まり、窓が発生するのです。
「上窓」と「下窓」の違い
窓には主に2種類あります。それぞれ意味合いが異なるので、きちんと区別して覚えましょう。
上窓(うわまど)=ギャップアップ
上窓とは、当日の始値が前日の高値よりも高く始まること。
投資家の「買いたい!」という意欲が強く、寄付きから株価が飛び跳ねる形になります。
例:前日高値 1,020円 → 当日始値 1,050円
これは、非常に強気な状況です。買いが先行し、上昇トレンドが加速するサインともいえます。
下窓(したまど)=ギャップダウン
下窓とは、当日の始値が前日の安値よりも安く始まること。
投資家の「売りたい!」という意識が強く、寄付きから下落してしまうパターンです。
例:前日安値 980円 → 当日始値 950円
下窓は、ネガティブなニュースや失望感、リスク回避などの「弱気相場」のサインとされます。
なぜ「窓」は重要視されるのか?
チャート上に現れる“窓(ギャップ)”は、単なる価格の空白ではありません。
そこには投資家たちの心理や、相場全体の流れを読むためのヒントが詰まっています。
窓は「強い意志の現れ」
窓が開くということは、前日までの価格帯を「飛び越える」ほどに投資家の買い(または売り)が集中したということです。
これはつまり、“市場の強い期待感”や“恐怖”が一方向に傾いた状態を表しています。
- 上窓:強い好材料に反応し、「この株はもっと上がるはず!」という期待が広がっている
- 下窓:悪材料が出て、「これ以上持っていられない」という投げ売りが出ている
このように、「窓」は単に価格差ではなく、感情のギャップ=心理の偏りを表しているのです。
価格帯別出来高を飛び越える意味
株価は、基本的に出来高(売買の量)が多い価格帯で「もみ合う」ことが多いです。
しかし、窓を開けて始まるということは、その“もみ合いの領域”を一気に突破している状態です。
これは、以下のような意味を持ちます:
- 多くの投資家がまだ売買していない価格帯に突入
- 上値抵抗線/下値支持線が機能しにくい
- 新たな需給のゾーンに突入している
このように、窓の発生は、トレンドの転換点であることも少なくありません。
窓ができる原因とは?

株価のギャップは、何の前触れもなく起こるわけではありません。
多くの場合、市場外のイベントや材料が影響しています。
代表的な原因を具体的に見ていきましょう。
決算発表・業績修正
株価に最もインパクトを与えるのが「企業の決算」です。
- サプライズ好決算 → 上窓
- 下方修正・赤字転落 → 下窓
決算は夕方に発表されるため、翌営業日の寄付きで投資家の反応が集中し、窓が発生することが多いです。
海外市場の影響
日本市場が閉まった後に、米国の株価(特にNASDAQやS&P500)が大きく動いた場合、それを反映して翌朝の日本株に窓が開くことがあります。
- 米国株の急騰 → 日本株も連動上昇(上窓)
- FRBの金利発表で急落 → 日本株も下窓
日本は米国の翌朝に取引が始まるため、「夜のニュースを翌朝に織り込む」という性質があるのです。
為替や原材料価格の変動
輸出入企業にとっては、為替(ドル円など)の動きが死活問題です。
- 円安が進行 → 輸出企業は上窓になりやすい
- 原油価格急騰 → 航空会社や運送業は下窓に
地政学的リスク・災害など突発的要因
地震やテロ、世界的な決定事項などで一気に株価が動く場合はあります。
- 大地震やテロなど → 一斉の投げ売りによる下窓
- G7・米中会談での合意報道 → 一斉の買い戻しによる上窓
突発的なニュースによって窓が開いた場合は、感情が先行しすぎて値動きが過剰になる傾向もあります。
窓を活用する3つの基本ルール
チャートに“窓”が現れたら、それは「投資家の感情が動いた証拠」です。
この窓をうまく使えば、売買のタイミングを判断するうえで非常に有利に働きます。
ここでは、初心者でも実践しやすい「窓を活用する3つの基本ルール」を紹介します。
ルール①:「窓は埋める」までが“ワンサイクル”と捉える
最も有名なテクニカル格言のひとつに「窓は埋めにくる」というものがあります。
これは、相場に開いたギャップ(=価格の空白)が、のちのち戻ってくる(=埋められる)傾向があるという意味です。
なぜ窓は埋まるのか?
- 上昇でできた窓 → 利益確定の売りが入り、押し目が入る
- 下落でできた窓 → 行き過ぎた売りが戻され、戻りが入る
つまり、投資家の「やりすぎ」を修正する自然な流れであり、窓ができた価格帯は“そのうち”また通過することが多いのです。
🔰 初心者向けの実践アドバイス:
- 窓が開いた当日は「追いかけない(エントリーを我慢)」
- 窓を埋める動きが始まったときに、買い/売りを検討
- 逆張りで狙う場合は、移動平均線や支持線で反転の兆しを確認
例:
- 前日終値:1,000円 → 翌朝始値:1,100円(上窓)
- 3日後に1,030円まで押してきた → 埋めにきている動き
- 押し目での買いを検討するチャンス
ルール②:「窓を埋めずに進む=本物のトレンド」
「窓は埋める」とはいえ、一部の窓は“埋めずに”そのまま上昇 or 下落を続けるケースもあります。
これは、材料やトレンドの強さが極めて強い証拠です。
埋めない窓が意味するもの:
- 市場がそれほどまでに強気/弱気である
- 窓を追いかけてでも買いたい/売りたいという心理
- いわば「本物のトレンド」が始まっている可能性
初心者向けの実践アドバイス:
- 窓を開けて“もみ合わず”にさらに進んでいるかどうかを観察
- 窓を埋めに戻ってこなければ「押し目待ちに押し目なし」状態
- この場合は、「高値掴みを怖がらず、トレンドに乗る判断」も必要
例:
- 好決算+来期大幅増益予想 → ギャップアップ+大陽線
- 翌日も高値更新 → 窓を埋めない → トレンドフォロー銘柄と判断
● ルール③:「窓付近は売買の攻防ゾーンになる」
窓を「埋めにきた」後の動きもまた、重要な売買サインです。
窓を埋めた地点では、
- 買い勢力と売り勢力がぶつかる「攻防エリア」
- 戻り売り/反発買い/リバウンド狙いなど様々な思惑が交錯
つまり、その後の値動きを見て“勝者”を見極める場所とも言えます。
初心者向けの実践アドバイス:
- 窓の埋めが完了したら「一呼吸」待つ
- 反発すれば上昇トレンド再開、割り込めば下落再開と判断
- この地点では、出来高やローソク足の形状が特に重要になる
例:
- 下落で空いた窓を埋めに戻る → ちょうどその価格で“上ヒゲ”をつけて反落 → 戻り売りのサイン
- 埋めた後に陽線連発 → 再上昇のきっかけに → 買いエントリーのチャンス
注意点:窓だけに頼らないこと!
いくら窓に法則性があるとはいえ、常に「窓=買い場 or 売り場」になるわけではありません。
- 窓埋めを待っていたら株価がそのまま急騰
- 窓を埋めにいったと思ったら、ダマシで反転
など、トレンドの初動や材料のインパクト次第で「教科書通りにいかない」場面も多いのが実際です。
そのため、以下のような複合的な視点を持つことが大切です。
- 出来高の増減
- 他のテクニカル指標(移動平均線・RSIなど)
- 時間帯や相場環境(決算期・地政学リスクなど)
まとめ
「窓」という概念は、最初はとっつきにくいかもしれません。
でも、一度その仕組みと意味を理解すれば、チャートの見え方がまったく違ってきます。
株価は、人の心理の集合体。その“感情の揺れ”が「窓」としてチャートに表れるのです。
ぜひ、これからはチャートを見るときに、
- 今日、窓が開いている?
- その窓は埋まりそう?
- 窓の背景にはどんなニュースがあった?
といった目線を持って、日々の株価観察に役立ててみてください。